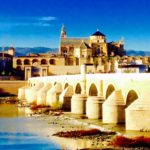2018/05/05

バルト三国(エストニア・ラトビア・リトアニア)と聞いても、「どこ?」と思う日本人は少なくないことでしょう。実はヨーロッパの中でも、これらの地域の認知度はまだまだ低いのが現状です。今回はなぜ「バルト三国」と呼ばれているのか、また各国民性についてご紹介します!(Latvia & Estonia& Lithuania in Baltic)
目次
20世紀に生まれた「三国ワンセット」
バルト海に面するエストニア・ラトビア・リトアニアが、三国ワンセットとして見られるようになったのは、第一次世界大戦後からのことで、ここ100年ほどの話になります。
この三国は中世から近世まで、それぞれが時期によってスウェーデンの支配下になったり、またはポーランドの支配下になったり、そしてロシアの支配下になったりしています。
かつては三国ともに旧ソ連に属していましたが、風景も気候もロシアとはかなり違います。教会の建物はロシア風のたまねぎ型の屋根ではなくて、天を突くようなドイツ風のゴシック建築が多いのが特徴です。
またバルト海に面しており、メキシコ暖流(大西洋を流れる暖流)の影響で、寒さもロシアの内陸ほど厳しくもありません。
三国で共通することは、歌を愛することです。旧ソ連からの独立時は武力に頼らない抵抗として、祖国の風景を歌う愛国的な唱歌や、民謡を合唱する運動で盛り上がりました。
バルト三国の民族性と言語
国民の気質は、エストニア人とラトビア人は北欧人らしく無口でシャイで、それに比べると、信仰深いカトリック信徒が多いリトアニア人は、感情豊かだと言われます。
三国で一部の単語は似ていますが、日常会話は大きく違います。例えば「ありがとう」はエストニア語では「アイタ」、ラトビア語では「パルディエス」、リトアニア語では「アチュウ」といったようにまったく別の言葉になります。
旧ソ連からの独立では力を合わせた三国ではありまあすが、仲が良いのかというと今では微妙です。
北のフィンランドと言葉や文化が近いエストニア人は、北欧に仲間意識を持ちますが、カトリック信徒が多いリトアニア人は西欧に仲間意識を持っていて、そして間に挟まれたラトビア人は「僕たち三国は仲間じゃなかったの?」とぼやく立場になっています。
IT先進国エストニアは貧しい国だった?
エストニアはときおり、旧ソ連圏きってのIT先進国と言われます。インターネット電話の「スカイプ」を開発した国で、官公庁では紙の書類は使わずに、他国に先駆けて2002年から電子投票を段階的に導入しています。
ところが首都タリンを一歩離れれば田舎なのも、エストニアの特徴です。国土は平野が多いのですが、大森林など手つかずの自然も多く残っています。
地方に行けば、おじいさんやおばあさんは都会の病院には行かずに、森に湧き出ている泉や虫を利用した、おまじないのような民間療法を行っていたりもしています。
今でこそハイテク立国のエストニアも、少し前までは非常に貧しかったのです。そのために食べ物をとても大切にします。その証拠に食事の前には「パンがずっと続きますように」と言います。
普通落とした食べ物は処分することが多くなっている今でも、エストニアではテーブルからパンが落ちたら、拾って口づけする習慣があるほどです。
エストニアのサウナは噂話の発信地
またエストニア人は、お隣のフィンランド人と同じくサウナが大好きです。昔からサウナは男同士、女同士が集まって裸で語り合う社交場でした。
エストニアでは「女の人たちがサウナで言っていたわよ」と言えば、現在のうわさ話をする時の「こんな話が流行っているんだけど」という意味のお決まりのフレーズになります。
おわりに
歴史を見るとバルト三国のなかでも、エストニア人は特に「自分たちは北欧の国」という気持ちが強いです。
エストニアは14世紀以降に、ドイツ騎士団領になったり、はたまたロシア領になったりしていますが、16~18世紀のスウェーデン支配の時代を、今でも「古き良きスウェーデン時代」と呼んでいます。それは当時はエストニア語が大切にされていたからなのです。
合わせて
バルト三国ベストシーズンとバルトの歌と踊りの祭典の世界遺産
バルト三国構成国の観光スポットと最短期間8日間モデルプラン
バルト三国タリン・リガ・ビリュニュスを繋ぐ人間の鎖と独立
琥珀の海沿岸に住むバルト民族の歌の祭典や職業の日の祝日
エストニアは北欧、カトリック信徒が多いリトアニア人は西欧に仲間意識を持つ
シャウレイ十字架の丘から見るリトアニアやバルト三国の国民性
も参考にしてみて下さいね!